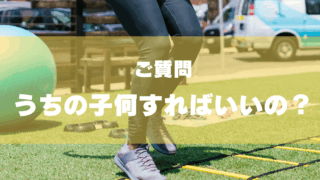戦術ついて書いていきます。そして、個人スポーツというよりはチームスポーツ【混戦型球技】について述べていこうと思います。サッカーを主語にして書きますが、この混戦型球技においては本質は同じと考えています。
僕は戦術を考える立場にありません。しかし、戦術を理解していないとトレーニングに支障が出るので最低限の戦術の理解をしています。データも取るしね。
日本をはじめとした東アジアの方達は自分と向き合うことが上手です。そして先進国では環境も整っています。それがそのまま個人競技のメダルに繋がっているのではないでしょうか。バドミントン、柔道、空手、フィギュアスケート、スケートボード、ボクシング、水泳など、、野球も局面では個人の戦いです。
武士の時代から死ぬ気で1対1をしてるので、そういったものが遺伝子レベルで受け継がれているのでしょうか。
これは僕の妄想ですが、サッカーやバスケの1on1の世界大会があったとしたら、金メダルをかなり早い段階でとるんじゃないかと思っています。
そういった意味でも「戦術」というものに馴染みのない方が多いかもしれません。
戦術とは。までの前置きが長めですが、読んでいただけると嬉しいです。
個のレベルは高い
チームスポーツにおいて日本人の個のレベルは高いと思います。ただうまければ勝てるわけではないのがチームスポーツの厄介なところです。
日本のサッカーのレベルは年々高くなっている。ように感じますが、頂点の選手のレベルが上がっただけで実はそんなに変わってないのではというのが僕の率直な感想です。
2024年度、国立競技場にて高校サッカー選手権の決勝戦を観戦しました。前橋育英vs流通経済大柏の試合で、スタジアムは超満員。その年のJリーグの最高動員数も超えていたそうです。
試合中は目が離せず、ずっと緊張感に包まれていました。試合が終わった後も感動の余韻に浸れるほどいい試合でした。
でも、高校生が頑張っているから。という感動の仕方でした。それはそれでいいのですが、批判を恐れずいうのであればレベルが低い。というより、一辺倒なサッカーを1試合見せられていたような感じでした。
ただ「個」という観点で見れば上手い子はいました。
迷いをなくすのが勝利のコツ
勝利のコツは迷いをなくすことです。選手の迷いは判断の遅れや、試合中のパフォーマンスに影響します。これはどのスポーツでも同じことです。
そして迷いをなくすと選手は100%でプレーすることができます。この時はこうする。それが分かっているからです。
サッカーではどんな時も「前に蹴る」戦術は強いです。技術はそれほど高くなくても、11人共通して同じ考えを持っているので息も合わせやすい。高校サッカーがほぼこの前に急ごうとする。ゴールまでの迷いをなくす。ゴールまでの最短の手段を選んでいるように感じました。
例えばサッカー日本代表のアジア予選。日本はアジアでは強豪国なので相手チームが、この「ひたすら前に蹴る」サッカーをしてきて苦戦します。
逆にW杯などで立場が変われば日本は強豪相手に「前に蹴る」サッカーを行います。
弱者が強者に勝つ、ジャイアントキリングの最も起こりやすい戦術だと思います。
転換期
しかし、ただひたすら前に蹴る単調なサッカーが選手を育てるかというと、そうではないと感覚的に理解できると思います。
日本もだんだんと強くなってきてそういった考えが広まっていきました。その1番の理由は日本人と体格が似たスペインがW杯で優勝したこと。
その代表の中心選手がFCバルセロナ出身だったことでパスを繋ぐのがサッカーの本質だと考える方が多かったんだと思います。
するとパスをつなぐサッカーが一気に日本に浸透しました。
でもパスするとなぜいいのか?
戦術は公式の組み合わせ
パスサッカーは迷いのオンパレードになります。どこに出すか、いつドリブルするか。パスサッカーが浸透していくと「なんかパスは回ってるけど、全然前に進んでねぇじゃん。」そんなチームが増えました。
戦術は公式の組み合わせです。
10という解がゴールと例えてみましょう。
その10という答えを出すためにどの式を使うかを監督が決め、選手が理解する。これが戦術だと思っています。
この10という答えを相手に合わせて無数にある数字や公式を変えていく。足し算・引き算・かけ算・わり算・その他の公式を使って準備する。ピッチで即興で作り上げていく。それが今世界のトップでプレーしている監督・選手なのです。
先ほど述べた前に蹴るサッカーを例に挙げると、基本的に足し算と引き算だけ。だから監督は指示しやすいし、選手は分かりやすい。意図のないパス回しも同じかもしれません。
足し算と引き算だけでは選手として上達はしません。その時の試合では良くても、この先も足し算引き算で選手として勝ち残っていくのは難しいのです。
またそこで育った選手はレベルが高くなった時に周りの話についていけない可能性があります。チームの中でずば抜けていて、強いチームに行ったのに活躍できない選手は戦術の積み重ねができていない可能性があります。
これはサッカーだけじゃないと思います。
戦術とは。
戦術は個を引き出し、試合に勝つための戦い方です。
これは監督の言いなりになれということではなく、チームの勝つための最低限のルールです。秩序の中に自由をつくり、迷いをなくし、選手のパフォーマンスを最大限発揮させます。
これをシーズンを通してトレーニングしていきます。
これを毎年、毎年積み重ねることで戦術のバリエーションが増えて、レベルの高い戦術に適応できるようなっていくのです。
時には、戦術と自分の能力のギャップに苦しむこともあるでしょう、それはどんなレベルの選手も一緒です。